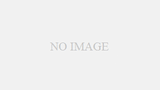SNSや口コミサイト、掲示板などでの情報発信が一般化するなか、企業にとって“ネットの声”は無視できない影響力を持っています。その中でよく混同されるのが「誹謗中傷」と「風評被害」という2つのリスク。しかし、それぞれの性質や法的な扱いには明確な違いがあります。本記事では、誹謗中傷と風評被害の違いを整理し、企業として正しく理解しておくべき線引きや対処の方向性をわかりやすく解説します。
誹謗中傷とは何か?法律で定義される“攻撃的な表現”
「誹謗中傷」とは、個人や企業に対して社会的評価を著しく損なわせるような言葉や行為を指し、主に法律の観点から違法性が問われる表現を含みます。具体的には、「名誉毀損」「侮辱」「信用毀損」「業務妨害」といった法的根拠に基づき、刑事・民事の責任を追及される可能性があるものです。
たとえば、事実に反して「〇〇会社は違法営業をしている」「社員が横領した」などと断定的に投稿することは、名誉毀損罪に該当するおそれがあります。仮に内容が事実であっても、その表現方法や意図によっては社会的評価の低下につながり、違法と判断されるケースも少なくありません。
また、法的に問題視されるのは、攻撃的な言葉や侮辱的な表現に限らず、あえて個人や法人を特定し、悪意ある文脈で繰り返し言及するような“執拗な言動”も含まれます。投稿が一度であっても、その拡散性が高く、企業の信用を大きく損なう場合は、被害として深刻な扱いを受けることになります。
誹謗中傷が明確に違法と判断されれば、投稿の削除だけでなく、発信者に対する損害賠償請求や刑事告訴などの対応も可能です。企業としては、「法的に対処可能な領域なのか」を判断するための視点を持つことが非常に重要になります。
風評被害とは?必ずしも違法ではない“拡散される印象”
風評被害とは、企業に対する事実・誤解・感情的な印象がネット上で拡散されることで、結果的に信用や業績に悪影響を及ぼす状況を指します。ポイントは、「内容が必ずしも違法とは言い切れない」「発信者が意図的な攻撃をしていない場合もある」という点です。
たとえば、「このお店は対応が遅くて不満だった」「思っていたより品質が良くなかった」といった口コミは、個人の主観的な感想であり、表現の自由の範囲とされています。こうした投稿がSNSやレビューサイトで共感を集めると、企業のイメージが低下し、来店数や問い合わせ件数が減少する、といった“間接的被害”が発生します。
風評被害は誹謗中傷と異なり、法的措置に踏み切るのが難しい場合が多いのが特徴です。書かれている内容に明らかな虚偽が含まれていない限り、削除申請も却下されるケースが多く、「合法だけれどダメージが大きい」という厄介なリスクです。
企業にとっての風評被害は、単なる批判やネガティブな意見であっても、無視できない経営課題です。とくに検索結果や口コミ評価に影響するため、新規顧客や求職者の判断にも直結します。違法ではないからと放置せず、早期に内容を把握し、必要に応じて正しい情報を発信することが、風評被害を最小限に抑える鍵となります。
企業にとって重要な“違法性”と“影響力”の見極め方
誹謗中傷と風評被害の違いを理解した上で、企業が現実的に対応を検討する際には、「違法性の有無」と「拡散・影響の規模」をセットで見極めることが不可欠です。違法であるかどうかは法的措置の判断材料に、拡散力の大小は対応の緊急度に直結するため、両方の軸でリスクを整理しておくことが重要です。
まず、違法性があるかどうかを判断するには、「投稿内容が虚偽かどうか」「社会的評価を不当に損なっているか」「投稿の目的に悪意があるか」といった視点からチェックします。特定の個人や法人名を挙げて中傷している場合は、名誉毀損などに該当する可能性が高く、弁護士など専門家への相談が推奨されます。
一方で、拡散力の大小も軽視できません。たとえ投稿自体に違法性が薄くても、影響力のあるインフルエンサーや大手メディアに取り上げられると、短時間で風評被害が拡大し、検索結果やブランドイメージに大きなダメージを与えかねません。逆に、内容に問題があっても、匿名掲示板の一過性の投稿であれば、様子を見て対応を見送るという判断も合理的です。
企業としては、「違法かつ影響が大きい場合」にはすぐに削除申請や法的措置を、「合法だが拡散が広がっている場合」には情報発信や逆SEOなどの防御策を取るなど、状況に応じた対応を使い分ける視点が必要です。
タイプごとに異なる対応策と企業の備え方とは
誹謗中傷と風評被害、それぞれのタイプに応じた対応策を整理しておくことで、いざという時に冷静に動ける体制が整います。企業がとるべき対応は、「削除・法的対応」と「印象回復・広報対応」に大きく分けられます。
誹謗中傷に対しては、削除申請が第一の対応になります。各SNSや口コミサイトには報告フォームが設けられており、違反理由と証拠(スクリーンショット、投稿リンクなど)を添えて削除依頼を出します。それでも削除されない場合には、弁護士に相談し、発信者情報の開示請求や損害賠償請求といった法的手段に踏み切ることも検討されます。
風評被害に対しては、正しい情報を発信して印象を整える広報的な対応が主になります。企業ブログやSNS、プレスリリースなどで事実関係を説明し、企業の誠実な姿勢を見せることで、誤解や偏った印象の修正を図ることができます。また、逆SEOによって検索結果にポジティブな情報を上位表示させ、ネガティブな内容の可視性を下げる手法も有効です。
加えて、日頃からの備えとしては、「社内のSNSリテラシー教育」「風評管理マニュアルの整備」「リスク監視体制(GoogleアラートやSNSモニタリング)」などを行っておくことが、スムーズな対応と早期発見につながります。
誹謗中傷と風評被害は、起きる前提で準備しておくことが肝心です。タイプに応じた適切な対応を取ることが、企業の信頼を守る一番の近道なのです。
まとめ
誹謗中傷と風評被害は、混同されがちな言葉ですが、その性質や対処法には明確な違いがあります。誹謗中傷は法的に違法性がある可能性があり、削除や訴訟といった対応が可能なケースが多い一方で、風評被害は合法でありながら企業イメージに大きなダメージを与える“見えにくい脅威”です。だからこそ、企業はこの2つのリスクを正しく区別し、それぞれに合った備えと対応を整えておくことが不可欠です。知識と準備があれば、万が一のときにも信頼を損なわず、冷静にリスクを乗り越えることができるはずです。